
餅がおいしいシーズンになりました。一方、年末年始は餅を喉に詰まらせて救急搬送される人が急増する時期でもあります。悪くすると命にかかわる事態にもなりかねませんが、餅を喉に詰まらせさえしなければ防ぐことができる事故です。
今回は、餅を喉に詰まらせないための方法として、食べ方の工夫や飲み込む力をキープできるトレーニングを紹介しましょう。
餅を喉に詰まるのはなぜ?
餅は喉に詰まりやすい食べ物
餅は意外と喉に詰まりやすい食べ物であるということをしっかり認知することが、事故を防ぐための第一歩です。
餅は柔らかい食べ物のようでありながら、噛み切ることは難しく、大きな塊のまま飲み込んでしまいがちです。
さらにねばねばしているため喉に貼りつきやすく、いったん喉に詰まらせてしまうと簡単には取り除けないのです。
人の喉は詰まりやすくできている
もしサルやイヌなどの動物が餅を食べたとしても、喉に詰まって窒息することはありません。
人も動物も食べたものや飲んだものは食道へ、空気は気管へ向かいます。ところが、動物の喉では食道への入り口と気管への入り口が立体交差していることに対し、人の喉では平面交差しているのです。
この違いは、人の喉だけに備わった声を出す機能によるものです。
人が食べ物を飲み込むときには気管側にフタがされるようになっているのですが、この動作がうまくいかないと誤嚥や窒息を引き起こすことになります。
つまり、呼吸・嚥下・発声をこなすための多機能となった人の喉はもともと誤作動しやすくできていて、餅などが喉に詰まるリスクは避けられないようになっているのです。
餅が喉に詰まらない食べ方とは

しゃべりながら食べない
食べ物や飲み物を飲み込んだとき気管にふたがされますが、おしゃべりしながら食べているとこの動作がうまくいきません。
さらにおしゃべりしていると、しっかりかまずに飲み込みがちにもなります。口にお餅が入っている間は、聞き役に回りましょう。
テレビを見ながら食べない
飲み込むときの姿勢も餅を喉に詰まらせないために大切で、背筋を伸ばしてあごを引いた姿勢が、スムーズな嚥下をうながします。
ところがテレビを見ながら食べていると、猫背であごが前に突き出た姿勢になりがちです。さらに、テレビに夢中になってしまい、しっかりかむことを忘れてしまう傾向もあります。
口のなかにお餅があるときには、意識をテレビではなく飲み込むことに向けましょう。
飲みこんでから次の餅を口に入れる
お餅を小さく切ることは、喉詰まりの予防に有効とされています。
けれども飲み込まないうちに次々と口に入れてしまうと、お餅が口の中で大きな塊になってしまうので、小さく切った意味がなくなってしまうのです。
口に入れたお餅がしっかり飲み込めたことを確認してから、次のお餅に取り掛かってください。
餅をひとりで食べることは危険
食べ物を喉に詰まらせてしまったとき、激しくむせることで吐き出すことができればよいのですが、それでも取れない場合は背中を叩いたり腹部を突き上げたりといった応急処置が有効です。
ところがこれらの処置は誰かがそばにいてくれなければ間に合いません。お餅は誰かと一緒に食べることをおすすめします。
▼念のため一度は見ておきたい応急処置法
餅を喉に詰まらせないためのトレーニング
鍛えるべきポイントは舌
飲み込みに必要な筋力を鍛えれば、餅が喉に詰まってしまうリスクを抑えることができます。
嚥下力を高めるため舌を大きく出すような体操が提唱されていますが、食べ物を喉のほうに送り込むとき舌は下方に下がりながら後方に移動します。
舌出し体操での動作は逆の動きになってしまっているので、もっと効果的な方法を考えたいところです。
舌のトレーニングにうってつけの「舌打ち」
そこでおすすめしたいのは「舌打ち」。
できるだけ大きな音が出るように舌を打ちますが、上あごにしっかり押し付けた舌を、勢いよく引き戻すように離すとうまくいきます。ただし、人前でやると「喧嘩売ってる?」と誤解されかねないのでご注意を…。
▼こんな道具もあります
口を閉じる運動も必要
飲み込む動作をするときには、口をしっかり閉じていないとうまくいきません。加齢と共に口元にしまりがなくなりますが、見た目だけでなく機能面でも問題ありです。
ぶくぶくうがいをするときに口から水が飛び出すようなら、トレーニングが必要でしょう。唇を閉じて、口の回りを内側から舌で押し出しながらぐるりと回す運動が効果的です。
おいしくお餅を食べてお正月を楽しく過ごしたい

自分の口で何でも食べられることは幸せ
お雑煮やぜんざいなどお餅を食べる機会がふえる年末年始ですが、喉に詰まらせて救急搬送なんてことになっては大変です。
とはいえ、お餅は危険だからと食べずにいるのは残念なことで、何でもおいしく食べられる幸せは失いたくありません。
ちょっとした注意や簡単なトレーニングで誤嚥を防いだり嚥下力を高めたりすることができるので、ぜひ取り組んでいただければと思います。
今日のボタモチ
今日のボタモチは【入り口】です。
消化器官の入り口である口がよく働いてくれると、あとの仕事が楽になります。口を鍛えることは意外と簡単にできるうえ、全身の老化を遅らせる効果もあるのです。これはやってみる価値がありますね。
※今日はボタモチ、2個追加!
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19be3fc9.9001200d.19be3fcb.4876224c/?me_id=1209540&item_id=10010621&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fokuchi%2Fcabinet%2Fitem_thumb%2Fimgrc0090278881.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

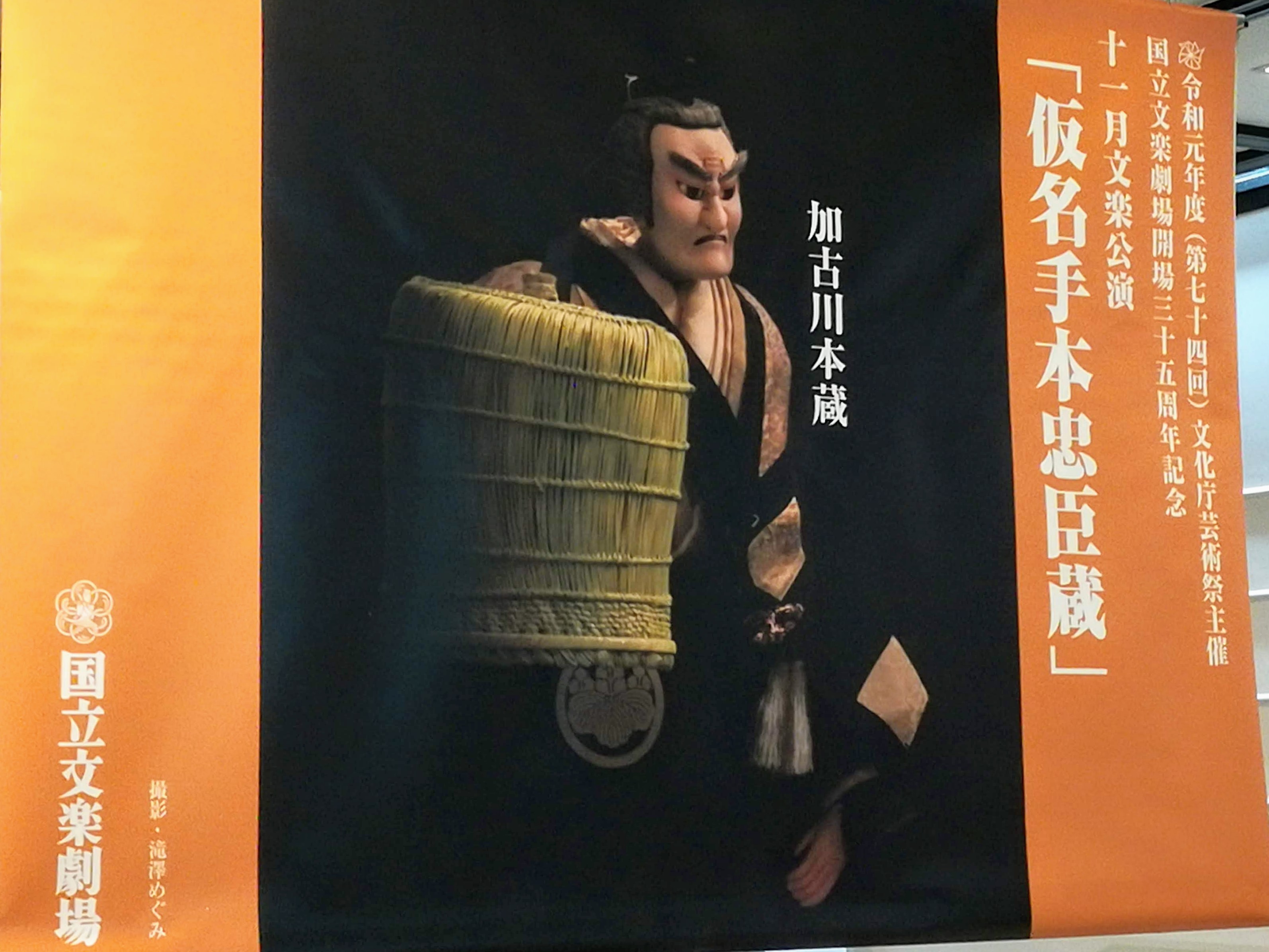

コメント